

|
アクセスカウンタ (since 2000/09/10) |
 トップページ
トップページ
 行事・活動紹介
行事・活動紹介
 行事日程
行事日程
 行事・活動
行事・活動
 地盤工学フォーラム
地盤工学フォーラム
 地盤工学講座
地盤工学講座
 地盤工学セミナー
地盤工学セミナー
 講習会・講演会・見学会
講習会・講演会・見学会
 学術活動
学術活動
 委員会活動
委員会活動
 調査・研究・出版物
調査・研究・出版物
 支部表彰
支部表彰
 受賞業績紹介
受賞業績紹介
 募集要項
募集要項
 社会貢献
社会貢献
 技術協力・連携
技術協力・連携
 出張講義のご案内
出張講義のご案内
 組織
組織
 沿革・規程等
沿革・規程等
 組織・役員・委員
組織・役員・委員
 東北支部 賛助団体 芳名録
東北支部 賛助団体 芳名録
 地盤工学会 特別会員(東北支部分)
地盤工学会 特別会員(東北支部分)
 地盤工学会 本部・各支部へのリンク
地盤工学会 本部・各支部へのリンク
 入会のご案内
入会のご案内
 入会案内はこちら
入会案内はこちら
 東北支部 賛助団体のご案内
東北支部 賛助団体のご案内
 バナー
バナー
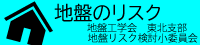


Copyright © 2006-2020 公益社団法人地盤工学会東北支部/Tohoku Branch of the Japanese Geotechnical Society. All Rights Reserved.
掲載日: 2016年6月6日(月)
最終更新日: 2016年6月6日(月)
地盤工学会東北支部 東北地域地盤災害研究委員会
地盤リスク検討小員会の発足と委員公募のお知らせ
|
公益社団法人 地盤工学会東北支部 東北地域地盤災害研究委員会 委員長 吉田 望 |
|
東北地方は過去にも自然災害に伴う被害を多く受けています。 最近で見ても,2011年東北地方太平洋沖地震は別格としても,2003年には一日に3回も震度6を記録する地震(宮城県北部),2005年には5月と7月に地震があり,2008年の岩手宮城内陸地震では荒戸沢ダムの背後で史上最大の崩壊が起こりました。 地震以外でも,昨年には蔵王の噴火も問題になりました。 また,2013年には秋田県で豪雨に伴う斜面災害,宮城県では2011年台風15号に伴う洪水,2015年には渋井川の決壊など多くの被害が発生しています。 人工の構造物は,作成時にいくらでも強くすることができますが,地盤はそうはいきません。 したがって,今後も地盤の変状に起因する被害は多く発生することと考えられます。 東北地域地盤災害研究委員会では,これまでは1978年宮城県沖地震の再来に備えて,X年宮城県沖地震小委員会を設置してきました。 しかし,上記の状況を考えると,活動範囲を地震に限定せず,地盤災害全体に広げるべきと考えました。 災害対策というと,災害が発生しない対策という事が第一に挙がってきますが,現実問題として過去の災害を見ると,災害の発生を完全に抑えることは不可能といえます。 ハザードとして災害をとらえることは重要ですが,リスクをきちんと評価し,その低減に努めるというのが現実的な考えと考えられます。 このような考えに基づき,東北地域地盤災害研究委員会内に「地盤リスク検討小委員会」を設置することといたしました。 活動内容は,日常活動としてリスクに関する勉強,広報,情報交換などを行い,地盤災害が発生したときには調査の拠点としての活動を想定しています。 日常活動は次の様なものを想定していますが,詳細は委員会の中で決めていきます。
|
|
東北地域の地盤災害減災に関わる技術者や,地盤災害の減災に興味を持つ技術者・研究者の積極的な参加を希望します。 応募書類には,氏名,年齢,所属会社名,連絡先 (e-mail),地盤災害の減災に関する経験(必要条件ではありません)や小委員会への参加の動機等(200字以内)を記して,下記の要領にて東北支部に提出をお願いいたします。 E-mailの場合には,タイトルを「地盤リスク検討小員会委員応募」としてください。 なお,通常活動費用は学会の経費から支出しますが,交通費など,個人の活動に要する費用は委員の負担となります。
また,活動を身のあるものにしたいので,正当な理由なく1年間に一度も参加できなかった委員の方につきましては,次年度以降の委員から抹消させていただくことを予めご了承ください。
委員として活動を希望される方は,ぜひ地盤工学会の会員登録をお願いいたします。
会員登録方法等は,地盤工学会ホームページの「入会案内」 |
| 記 | |
|---|---|
| 委員応募締切り: | 平成28年6月25日(土) 17時 |
| 書類提出先: |
公益社団法人 地盤工学会東北支部 「地盤リスク検討小員会委員応募」
〒980-0014 仙台市青葉区本町2-5-1 オーク仙台ビル3階
E-mail: jgsb-th@tohokushibu.jp
電話: 022-711-6033 / FAX: 022-263-8363
|
| 以上 | |