

|
アクセスカウンタ (since 2000/09/10) |
 トップページ
トップページ
 行事・活動紹介
行事・活動紹介
 行事日程
行事日程
 行事・活動
行事・活動
 地盤工学フォーラム
地盤工学フォーラム
 地盤工学講座
地盤工学講座
 地盤工学セミナー
地盤工学セミナー
 講習会・講演会・見学会
講習会・講演会・見学会
 学術活動
学術活動
 委員会活動
委員会活動
 調査・研究・出版物
調査・研究・出版物
 支部表彰
支部表彰
 受賞業績紹介
受賞業績紹介
 募集要項
募集要項
 社会貢献
社会貢献
 技術協力・連携
技術協力・連携
 出張講義のご案内
出張講義のご案内
 組織
組織
 沿革・規程等
沿革・規程等
 組織・役員・委員
組織・役員・委員
 東北支部 賛助団体 芳名録
東北支部 賛助団体 芳名録
 地盤工学会 特別会員(東北支部分)
地盤工学会 特別会員(東北支部分)
 地盤工学会 本部・各支部へのリンク
地盤工学会 本部・各支部へのリンク
 入会のご案内
入会のご案内
 入会案内はこちら
入会案内はこちら
 東北支部 賛助団体のご案内
東北支部 賛助団体のご案内
 バナー
バナー
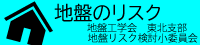


Copyright © 2006-2020 公益社団法人地盤工学会東北支部/Tohoku Branch of the Japanese Geotechnical Society. All Rights Reserved.
掲載日:2022年4月25日(月)
最終更新日:2022年4月25日(月)
|
地盤工学会東北支部では,地盤工学に関する身近で地域に密着した事業・研究等を通じ,会員の専門技術力の向上,調査・設計・施工等の効率化・レベルの向上,地盤工学のPR・イメージ向上などに貢献した優れた業績を毎年度表彰しております。 表彰候補の公募を行い,地盤工学フォーラムでの発表と応募書類に基づき表彰委員会において審査を行い,受賞者を決定します。 例年4月に開催される東北支部総会で表彰式が行われ,受賞者には表彰状と記念品が贈呈されます。 令和3年度は以下の通り授賞を行いました。その業績をここに紹介します。 令和3年度 地盤工学会東北支部表彰(技術的業績部門) |
(参考) 歴代受賞業績紹介 / 募集要項,表彰規定等 |
スレーキング性を有する高速道路盛土の劣化を考慮した維持管理手法に関する提案
| 受賞者: | 澤野 幸輝 | (株式会社ネクスコエンジニアリング東北) |
|---|---|---|
| 長尾 和之 | (東日本高速道路株式会社) | |
| 加村 晃良 | (東北大学) |
|
スレーキング性を有する母材を用いた盛土は,経時的な力学挙動の変化とそれに伴う変状が懸念されるため,長期的な維持管理の観点で,管理指標の定量化に課題があった. さらに,従来のスレーキング率試験は,力学特性の変化までを評価できないという問題もあった. 本研究は,①粒径9.5mm以下の粒度試料のスレーキングによる細粒化過程,②乾湿履歴が異なる試料を用いた三軸試験(CD),③同一供試体を用いて給排水繰返しベンダーエレメント試験, ④表面波探査によるスレーキング性を有する盛土の原位置計測を行い,盛土劣化の評価手法と健全度の評価手法の提案を行った. これらの結果から,スレーキングによる盛土材の変化と盛土内に生じる変化をまとめ,建設段階における盛土劣化の評価手法と,管理段階の健全度の評価手法を提案した. なお,本研究の一部は,科学研究費補助金(20K14820)を受けて実施されたものであり,ここに記して謝意を表する. |
|
国道401号博士峠における長大トンネルの施工実績
| 受賞者: | 熊坂 秀人 | (福島県会津若松建設事務所) |
|---|---|---|
| 中西 祐輔 | (鹿島建設株式会社) | |
| 金山 哲也 | (鹿島建設株式会社) | |
| 井上 勇太 | (鹿島建設株式会社) | |
| 月崎 良一 | (鹿島建設株式会社) |
|
本工事は福島県が事業主体として進めている「国道401号博士峠工区(路線延長L=約7.4km)」に含まれる「博士トンネル(延長L=4,503m)」のうち、起点(会津美里町)側の延長2,238mをNATM工法で施工する長大トンネルである。 現道の道路線形は著しく蛇行し、冬期は積雪により通行止めとなるため、通年での安全通行が可能となる博士峠工区の早期開通が求められている。 工事着手後、20N/mm2 程度と想定されていた地山強度が約 80 N/mm2 と高かったことから、当初計画の機械掘削では約9ヶ月の工程遅延が予測され、粉塵、振動による安全・環境の課題も発生した。 そこで、掘削工法を発破掘削に変更するとともに、坑内ダンプトラックを10t車から25t車への大型化、走行性向上のためにインバート工の片側半線施工などを採用し、掘削ずり運搬の効率化を図り、トンネル貫通点への到達を予定工期よりも約3ヶ月短縮させた。 |
|
鋼製エレメントの複数同時けん引による線路下横断道路
| 受賞者: | 川崎 拓哉 | (東日本旅客鉄道株式会社) |
|---|---|---|
| 池野 誠司 | (東日本旅客鉄道株式会社) | |
| 古宮 堅太郎 | (東日本旅客鉄道株式会社) | |
| 加藤 佑基 | (東日本旅客鉄道株式会社) | |
| 丸子 文之 | (東日本旅客鉄道株式会社) |
|
国土交通省東北地方整備局は東日本大震災における被害を受け、一級河川旧北上川の河口部の無堤防区間における築堤事業を進めている。 当社では、JR石巻線に近接する「築堤」と「こ道橋」を国交省から受託施工し、こ道橋新設工事では角型鋼管を地中に順次けん引することで函体を構築するHEP&JES 工法を採用した。 当該箇所は土被りが0.5 mと薄く、岩ずり混入が確認された鉄道盛土での施工となった。 通常、掘削・けん引による軌道影響が大きい上床版の角型鋼管の施工は、夜間の線路閉鎖間合での作業としているため、作業時間の制約による工期の増大が懸念された。 河川堤防工事の早期完成に向け,通常一本ずつ行う上床版の角型鋼管の掘削・けん引を複数本同時に行う新工法を本工事で初めて適用した。 この結果、軌道影響を与えずに従来工法と同等のけん引精度を確保しつつ、1.5倍の施工速度での掘削・けん引を実現し、復興事業の早期整備に貢献した。 |
|