

|
アクセスカウンタ (since 2000/09/10) |
 トップページ
トップページ
 行事・活動紹介
行事・活動紹介
 行事日程
行事日程
 行事・活動
行事・活動
 地盤工学フォーラム
地盤工学フォーラム
 地盤工学講座
地盤工学講座
 地盤工学セミナー
地盤工学セミナー
 講習会・講演会・見学会
講習会・講演会・見学会
 学術活動
学術活動
 委員会活動
委員会活動
 調査・研究・出版物
調査・研究・出版物
 支部表彰
支部表彰
 受賞業績紹介
受賞業績紹介
 募集要項
募集要項
 社会貢献
社会貢献
 技術協力・連携
技術協力・連携
 出張講義のご案内
出張講義のご案内
 組織
組織
 沿革・規程等
沿革・規程等
 組織・役員・委員
組織・役員・委員
 東北支部 賛助団体 芳名録
東北支部 賛助団体 芳名録
 地盤工学会 特別会員(東北支部分)
地盤工学会 特別会員(東北支部分)
 地盤工学会 本部・各支部へのリンク
地盤工学会 本部・各支部へのリンク
 入会のご案内
入会のご案内
 入会案内はこちら
入会案内はこちら
 東北支部 賛助団体のご案内
東北支部 賛助団体のご案内
 バナー
バナー
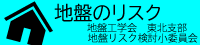


Copyright © 2006-2020 公益社団法人地盤工学会東北支部/Tohoku Branch of the Japanese Geotechnical Society. All Rights Reserved.
掲載日:2021年6月15日(火)
最終更新日:2021年6月15日(火)
|
地盤工学会東北支部では,地盤工学に関する身近で地域に密着した事業・研究等を通じ,会員の専門技術力の向上,調査・設計・施工等の効率化・レベルの向上,地盤工学のPR・イメージ向上などに貢献した優れた業績を毎年度表彰しております。表彰候補の公募を行い,地盤工学フォーラムでの発表と応募書類に基づき表彰委員会において審査を行い,受賞者を決定します。例年4月に開催される東北支部総会で表彰式が行われ,受賞者には表彰状と記念品が贈呈されます。 令和2年度は以下の通り授賞を行いました。その業績をここに紹介します。 令和2年度 地盤工学会東北支部表彰(技術的業績部門) |
(参考) 歴代受賞業績紹介 / 募集要項,表彰規定等 |
新規開発された原位置三軸試験による火山砕屑岩の力学特性評価及び検証
| 受賞者: | 大井 翔平 | (東北電力株式会社) |
|---|---|---|
| 伊藤 悟郎 | (東北電力株式会社) | |
| 岡田 哲実 | (一般財団法人電力中央研究所) | |
| 澤田 喬彰 | (株式会社ダイヤコンサルタント) |
|
硬質岩盤の強度・変形特性は,岩盤の潜在亀裂や礫の混入による不均質性を適切に考慮できるよう,原位置において,比較的大きな供試体に対して行うロックせん断試験や平板載荷試験の岩盤試験によって評価されている。 岩盤試験により求められる強度等は,地盤の安定性評価に大きな影響を与えるが,応力−ひずみ関係が直接求められないことや,強度の過小評価の可能性等の課題が指摘されている。 本研究では,上記の課題解決を目的に開発された,室内三軸試験と同様に応力−ひずみ関係を直接評価できる原位置三軸試験を用いて,凝灰岩及び火山礫凝灰岩の2岩種を対象に試験を行い,強度・変形特性を評価した。 また,過去に実施した岩盤試験の結果との比較検証を行い,破壊強度や弾性係数の妥当性を確認するとともに,原位置岩盤における応力−ひずみ関係を直接得ることが出来た。 また,既往試験による残留強度が過小評価されていることを示すことが出来た。 |
|
山形県内陸部の山岳地帯における風力発電所の建設
| 受賞者: | 平岡 伸哉 | (鹿島建設株式会社) |
|---|---|---|
| 新海 貴史 | (鹿島建設株式会社) | |
| 村田 和也 | (鹿島建設株式会社) | |
| 渡部 優 | (鹿島建設株式会社) |
|
いちご米沢板谷ECO発電所建設工事は、山形県米沢市板谷地区の標高約800mの山岳地帯に、出力2,000kWの風力発電機4基を建設する工事である。 当地域は国有林・保安林を含むため、開発面積や造成土量を低減し、周辺環境への影響を最小限にする必要があった。 また、発電量の増強を目的に風車のハブ(軸と羽根の連結部分)の位置をより高く、ローター面積(羽根の回転円の面積)をより大きくする近年の風力発電の傾向を反映した発電機仕様であったことから、大型部材の組立と輸送を山岳地帯で行うことが求められた。 そこで、山岳地帯における大型風力発電機組立に適応させたタワークレーンを用いた支持地盤の安定確保とクレーンの組立移動方法、国有林・保安林の環境を考慮した道路造成等の施工方法、長距離約90kmの山間部道路を使用した風力発電機部材輸送など施工方法を工夫し、良好な結果を得ることができた。 |
|
100mを超える軟弱層厚の超軟弱地盤における真空圧密工法を用いた高速道路盛土の建設
| 受賞者: | 上山 満 | (東日本高速道路株式会社 山形管理事務所) |
|---|---|---|
| 佐々木徹 | (株式会社大林組) | |
| 澤野 幸輝 | (株式会社ネクスコ・エンジニアリング東北 秋田事業所) |
|
東北中央自動車道 南陽高畠IC〜山形上山IC区間の起点側の約2kmの範囲は、有機質土や粘性土が100m以上の厚さで堆積している日本有数の軟弱地盤地帯であり、地盤上の盛土建設を行うため、地盤の安定性及び供用後の長期沈下が問題であった。 本工事では、本体工事に先立って実施した試験工事により得られた知見をふまえ、本体盛土計画を見直し、ドレーン改良深度が最大36mという日本最大級の真空圧密工法を用いた盛土の施工により高速道路を建設したものである。 施工時は、地盤内に作用する真空圧、盛土荷重、地盤内に発生する間隙水圧に着目した真空圧密工法独自の軟弱地盤上の盛土施工の安定管理を行うことにより、最大45cm/日の盛土が可能になり、安定を確保した盛土施工及び盛土工期を短縮することができた。 今回の成果により、国内外の軟弱地盤上の道路建設工事の対策技術として今後の発展に大きく寄与するものである。 |
|
BRT専用道路へのEPS工法の活用
| 受賞者: | 八代 星人 | (東日本旅客鉄道株式会社 東北工事事務所) |
|---|---|---|
| 湯浅 誠一 | (東日本旅客鉄道株式会社 東北工事事務所) | |
| 藤原 康成 | (東日本旅客鉄道株式会社 東北工事事務所) | |
| 北野 雅幸 | (東日本旅客鉄道株式会社 東北工事事務所) |
|
東日本大震災で被災したJR 気仙沼線の一部区間は,BRT*1として復旧することとなった。鉄道線路のBRT 専用道路への改築を進める中で,現地の状況により道路縦断の扛上が必要となった区間において,初めてEPS工法*2を採用した。 河川・道路交差部において堤防嵩上げに伴い約1mの扛上が必要となった。EPS工法を採用することにより,従前の荷重(活荷重+死荷重)を増加させずに扛上をすることが可能となり,既設構造物を有効活用し,工期短縮をすることができた。 また,橋台背面の盛土をEPSに置き換えることにより,土圧を軽減するとともに,5種類の密度のEPSをタイヤ荷重の分散状況に応じて使い分け,経済性に配慮した。 同様の扛上が必要となった市街地では,約500mの区間にEPS工法を採用し,その高い自立性を活用し,限られた用地内において扛上を行った。 また作業を人力主体とし,狭隘な施工環境での施工,騒音・振動の抑制を実現した。 *1 Bus Rapid Transit:バス高速輸送システム,*2 Expanded Poly-Styrol工法 |
|