

|
アクセスカウンタ (since 2000/09/10) |
 トップページ
トップページ
 行事・活動紹介
行事・活動紹介
 行事日程
行事日程
 行事・活動
行事・活動
 地盤工学フォーラム
地盤工学フォーラム
 地盤工学講座
地盤工学講座
 地盤工学セミナー
地盤工学セミナー
 講習会・講演会・見学会
講習会・講演会・見学会
 学術活動
学術活動
 委員会活動
委員会活動
 調査・研究・出版物
調査・研究・出版物
 支部表彰
支部表彰
 受賞業績紹介
受賞業績紹介
 募集要項
募集要項
 社会貢献
社会貢献
 技術協力・連携
技術協力・連携
 出張講義のご案内
出張講義のご案内
 組織
組織
 沿革・規程等
沿革・規程等
 組織・役員・委員
組織・役員・委員
 東北支部 賛助団体 芳名録
東北支部 賛助団体 芳名録
 地盤工学会 特別会員(東北支部分)
地盤工学会 特別会員(東北支部分)
 地盤工学会 本部・各支部へのリンク
地盤工学会 本部・各支部へのリンク
 入会のご案内
入会のご案内
 入会案内はこちら
入会案内はこちら
 東北支部 賛助団体のご案内
東北支部 賛助団体のご案内
 バナー
バナー
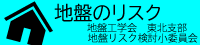


Copyright © 2006-2020 公益社団法人地盤工学会東北支部/Tohoku Branch of the Japanese Geotechnical Society. All Rights Reserved.
掲載日:2020年6月1日(月)
最終更新日:2020年6月1日(月)
|
地盤工学会東北支部では,地盤工学に関する身近で地域に密着した事業・研究等を通じ,会員の専門技術力の向上,調査・設計・施工等の効率化・レベルの向上,地盤工学のPR・イメージ向上などに貢献した優れた業績を毎年度表彰しております。表彰候補の公募を行い,地盤工学フォーラムでの発表と応募書類に基づき表彰委員会において審査を行い,受賞者を決定します。例年4月に開催される東北支部総会で表彰式が行われ,受賞者には表彰状と記念品が贈呈されます。 令和元年度は以下の通り授賞を行いました。その業績をここに紹介します。 令和元年度 地盤工学会東北支部表彰(技術的業績部門) |
(参考) 歴代受賞業績紹介 / 募集要項,表彰規定等 |
付加体を貫く長大トンネルにおけるコンピュータジャンボを活用した情報化施工
| 受賞者: | 高澤 哲哉 | (国土交通省東北地方整備局) |
|---|---|---|
| 西川 幸一 | (鹿島建設株式会社) | |
| 宮嶋 保幸 | (鹿島建設株式会社) | |
| 川野 広道 | (鹿島建設株式会社) |
|
復興支援道路宮古盛岡横断道路 新区界トンネルは、岩手県宮古市区界地区〜盛岡市簗川地区間における延長4,998mの本坑と5,045mの避難坑及び避難連絡坑13本をNATMによる長大道路トンネルである。 復興支援道路のため、本坑を早期掘削が求められており、そのためフルオートコンピュータージャンボ等を利用した地山評価技術による合理化情報化施工を実施した。 具体的には発破用穿孔とロックボルト穿孔時に破壊エネルギーを取り、そのデータより地山強度分布の統計学的解析による地山評価と補助工法の選定及び予測結果を技術者と作業員で共有し、安全性と品質を向上させ工期短縮し無事終了することが出来た。 |
|
先行盛土の沈下計測に基づく杭基礎の合理化
| 受賞者: | 永井 志功 | (東北電力株式会社上越火力発電所土木建築課) |
|---|---|---|
| 阿部 俊逸 | (東北電力株式会社上越火力発電所土木建築課) | |
| 大井 翔平 | (東北電力株式会社発電・販売カンパニー土木建築部火力原子力土木) | |
| 鈴木 直子 | (株式会社大林組技術研究所地盤技術研究部) | |
| 田摩 仁 | (株式会社大林組生産技術本部設計三部) |
|
東北電力(株)上越火力発電所新設工事における重要設備基礎には杭基礎を採用する計画であった。 杭の仕様や杭長の決定にあたっては、十分な地盤強度を有する支持層レベルの評価のほか、計画敷地高さへの嵩上げによる沖積粘土層の圧密沈下を適切に評価することが求められた。 圧密沈下量を過大に評価すると、杭に作用する多大なネガティブフリクションに対し設計支持力を確保するために杭長が長くなり、杭施工時のリスクや工期、コストが増加することが課題となった。 そこで、盛土荷重に対する沈下挙動を把握するため、先行盛土を実施し、地表面および地中部の沈下を計測するとともに、土水連成3次元FEMによる計測結果の再現解析を行い将来の沈下予測と沈下メカニズムを解明した。 今回の成果により、安全かつ合理的な杭の設計が可能となり、重要設備基礎杭の合理化による工程短縮および工事費の削減を図ることができた。 |
|
内海橋災害復旧工事における地盤改良工について〜CI-CMC工法の適用事例〜
| 受賞者: | 中出 雄也 | (株式会社不動テトラ) |
|---|---|---|
| 高山 英作 | (株式会社不動テトラ) | |
| 尾崎 太紀 | (株式会社不動テトラ) | |
| 吉田 昌平 | (宮城県東部土木事務所) | |
| 飯田 典由 | (若生工業株式会社) |
|
石巻市の中心部に位置する内海橋の災害復旧工事において、橋台背面の側方移動対策、道路盛土やBOXカルバートによる圧密沈下対策として、CI-CMC工法による深層混合処理工法が計画されていた。 工事位置である旧北上川河口部は、軟弱沖積層が50m近く堆積している地盤条件であった。 また、施工エリアは、既設家屋や供用道路が点在しており、かつ地盤改良に先立って新設橋台が立ち上がっている状況であり、長尺施工時に伴う変位影響が課題であった。 課題解決手段として、CI-CMC工法の特性を活かした独自の配合仕様を設定し、品質確保と低変位施工の実現を試みた。実施工においては、試験施工にて配合仕様の妥当性を確認し、施工を行った。 その結果、非常に厳しい施工条件下における長尺施工においても、周辺に有害な変位施工影響を及ぼすことなく、高品質な改良地盤を造成し工事を無事に終えることができた。 |
|
鉄道線路のBRT専用道路への改築に伴う路床改良方法の確立
| 受賞者: | 坂本 浩貴 | (東日本旅客鉄道株式会社東北工事事務所) |
|---|---|---|
| 北村 尚士 | (東日本旅客鉄道株式会社東北工事事務所) | |
| 阿部 哲 | (東日本旅客鉄道株式会社東北工事事務所) | |
| 北野 雅幸 | (東日本旅客鉄道株式会社東北工事事務所) |
|
東日本大震災により被害を受けたJR気仙沼線・大船渡線は、BRT(バス高速輸送システム)で復旧する方針が決まり、線路を専用道路に改築することとなった。 当初、線路をすべて撤去し道路を新設する計画であったが、工程短縮が強く求められたことから、バラスト(線路の砕石)を撤去せず、現位置で活用する方法を検討した。 バラストの道路の「路盤材」への活用は粒径の問題から困難であったが、「路床」への活用には粒径などの問題がなく可能であることが判明した。 路床改良の際に、バラストとセメント系固化材をスタビライザーでいっしょに攪拌・混合し、工程短縮を実現した。 この方法を標準として、これまでに約85.2kmの専用道路を整備した。最初の施工から7年が経過するが路床改良に起因する問題は発生していない。 今後、地方交通サービス維持のため、鉄道をBRTに転換することが一つの選択肢として考えられるが、その場合、本工法は広く適用可能であると考える。 |
|