

|
アクセスカウンタ (since 2000/09/10) |
 トップページ
トップページ
 行事・活動紹介
行事・活動紹介
 行事日程
行事日程
 行事・活動
行事・活動
 地盤工学フォーラム
地盤工学フォーラム
 地盤工学講座
地盤工学講座
 地盤工学セミナー
地盤工学セミナー
 講習会・講演会・見学会
講習会・講演会・見学会
 学術活動
学術活動
 委員会活動
委員会活動
 調査・研究・出版物
調査・研究・出版物
 支部表彰
支部表彰
 受賞業績紹介
受賞業績紹介
 募集要項
募集要項
 社会貢献
社会貢献
 技術協力・連携
技術協力・連携
 出張講義のご案内
出張講義のご案内
 組織
組織
 沿革・規程等
沿革・規程等
 組織・役員・委員
組織・役員・委員
 東北支部 賛助団体 芳名録
東北支部 賛助団体 芳名録
 地盤工学会 特別会員(東北支部分)
地盤工学会 特別会員(東北支部分)
 地盤工学会 本部・各支部へのリンク
地盤工学会 本部・各支部へのリンク
 入会のご案内
入会のご案内
 入会案内はこちら
入会案内はこちら
 東北支部 賛助団体のご案内
東北支部 賛助団体のご案内
 バナー
バナー
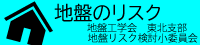


Copyright © 2006-2020 公益社団法人地盤工学会東北支部/Tohoku Branch of the Japanese Geotechnical Society. All Rights Reserved.
掲載日:2019年5月7日(火)
最終更新日:2019年5月7日(火)
|
地盤工学会東北支部では,地盤工学に関する身近で地域に密着した事業・研究等を通じ,会員の専門技術力の向上,調査・設計・施工等の効率化・レベルの向上,地盤工学のPR・イメージ向上などに貢献した優れた業績を毎年度表彰しております。表彰候補の公募を行い,地盤工学フォーラムでの発表と応募書類に基づき表彰委員会において審査を行い,受賞者を決定します。例年4月に開催される東北支部総会で表彰式が行われ,受賞者には表彰状と記念品が贈呈されます。 平成30年度は以下の通り授賞を行いました。その業績をここに紹介します。 平成30年度 地盤工学会東北支部表彰(技術的業績部門) |
(参考) 歴代受賞業績紹介 / 募集要項,表彰規定等 |
小土被り・強酸性土壌・酸性水を伴う高速道路トンネルの掘削 -山形蔵王トンネルの対策事例-
| 受賞者: | 保坂 浩寿 | (東日本高速道路株式会社 山形工事事務所) |
|---|---|---|
| 福士 森政 | (東日本高速道路株式会社 山形工事事務所) | |
| 髙松 雅宏 | (株式会社熊谷組やまがたざおう工事所) | |
| 星 太一 | (株式会社熊谷組やまがたざおう工事所) | |
| 千坂 俊治 | (東日本高速道路株式会社 東北支社) |
|
東北中央自動車道 かみのやま温泉~山形上山間における山形蔵王トンネルは、延長944mのNATMによる高速道路トンネルである。本トンネルの直上には一級河川酢川、名門ゴルフ場と国道13号が交差している。なお,本トンネルはほぼ全区間にわたり土かぶりが1.5D以下であり、一番土被りの小さい箇所は、酢川および国道13号部の1D程度であった。 また、本トンネルは蔵王山系の山体崩壊を起源とする扇状地形に位置し、酢川泥流堆積物および凝灰角礫岩が主に分布しており、時には想定を超える転石も出現した。さらに蔵王火山の下流に位置する酢川は強酸性河川でもあった。 これら小土被り・強酸性土壌・酸性水等の諸条件を抱えていたため、掘削した地山の状況(地層や亀裂)および地山内の地下水位や動態観測による切羽の状況を常時把握することで、効果的な補助工法の施工範囲等を決定させ、無事貫通を迎えることができた。 |
|
津波により全23連が落橋した鉄道橋下部工の早期復旧工事
| 受賞者: | 瀧内 義男 | (東日本旅客鉄道株式会社東北工事事務所) |
|---|---|---|
| 大武 博史 | (東日本旅客鉄道株式会社東北工事事務所) | |
| 舟腰 憲二 | (東日本旅客鉄道株式会社東北工事事務所) | |
| 木村 正喜 | (東日本旅客鉄道株式会社東北工事事務所) |
|
東北地方太平洋沖地震に伴う津波により甚大な被害を受けた、JR山田線宮古・釜石間(延長55.4km)の区間で最長の大槌川橋りょう(橋長375m、23径間)は、津波によって鋼桁23連全てが落橋、橋台・橋脚は24基中10基が倒壊、2基が傾斜し、山田線復旧における全体工程のクリティカルであった。 鮭や鮎が遡上する当該河川においては、河川内作業に規制期間があるなど工程的な制約が厳しい中、様々な損傷程度の橋脚をいかにして原形復旧するかが課題であり、以下の取組みを行った。 上記の取組みにより、制約条件の厳しい長大河川橋りょうの復旧を目標工期内で完了し、2019年3月23日に三陸鉄道リアス線としての運転再開を果たした。 |
|
フライアッシュを用いた土質改良工法の有効性について
| 受賞者: | 熊谷 洋 | (東北電力株式会社研究開発センター電源・環境) |
|---|---|---|
| 水沢 和仁 | (東北電力株式会発電・販売カンパニー土木建築部火力原子力土木G) | |
| 片田 吉孝 | (株式会社東北ロンテック) | |
| 佐藤 公之 | (株式会社ネイティブ・スペース) |
|
フライアッシュ(以下「石炭灰」という。)を主原料として固化材や不溶化剤などを配合した土質改良材は,石炭灰の有効活用技術の一つであり,従来工法より安心かつ安価な土質改良工法(レストム工法)を提供することで産業廃棄物量の抑制にも寄与することが出来る。一方,石炭灰に含まれる重金属の溶出特性は火力発電所や炭種毎に異なるため,同工法の積極的な採用にあたっては,重金属の溶出を確実に抑制する配合が必要と判断された。 そこで,東北電力㈱の石炭火力発電所から排出される石炭灰の同土質改良材への適用を図るため,室内試験により環境安全性が最も厳しい炭種を対象に溶出特性と強度特性の評価を実施した。次に室内試験で得られた有力な配合を対象に実機を用いたフィールド試験により溶出抑制効果や土質改良効果を確認し,最適な土質改良材仕様の選定を行い,標準配合を定めた。さらに,溶出抑制向上の観点から固化材を高炉セメントとした。これにより,安全かつ安価な利活用が可能となった。 |
|