

|
アクセスカウンタ (since 2000/09/10) |
 トップページ
トップページ
 行事・活動紹介
行事・活動紹介
 行事日程
行事日程
 行事・活動
行事・活動
 地盤工学フォーラム
地盤工学フォーラム
 地盤工学講座
地盤工学講座
 地盤工学セミナー
地盤工学セミナー
 講習会・講演会・見学会
講習会・講演会・見学会
 学術活動
学術活動
 委員会活動
委員会活動
 調査・研究・出版物
調査・研究・出版物
 支部表彰
支部表彰
 受賞業績紹介
受賞業績紹介
 募集要項
募集要項
 社会貢献
社会貢献
 技術協力・連携
技術協力・連携
 出張講義のご案内
出張講義のご案内
 組織
組織
 沿革・規程等
沿革・規程等
 組織・役員・委員
組織・役員・委員
 東北支部 賛助団体 芳名録
東北支部 賛助団体 芳名録
 地盤工学会 特別会員(東北支部分)
地盤工学会 特別会員(東北支部分)
 地盤工学会 本部・各支部へのリンク
地盤工学会 本部・各支部へのリンク
 入会のご案内
入会のご案内
 入会案内はこちら
入会案内はこちら
 東北支部 賛助団体のご案内
東北支部 賛助団体のご案内
 バナー
バナー
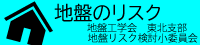


Copyright © 2006-2020 公益社団法人地盤工学会東北支部/Tohoku Branch of the Japanese Geotechnical Society. All Rights Reserved.
掲載日:2016年4月26日(火)
最終更新日:2016年5月16日(月)
|
地盤工学会東北支部では,地盤工学に関する身近で地域に密着した事業・研究等を通じ,会員の専門技術力の向上,調査・設計・施工等の効率化・レベルの向上,地盤工学のPR・イメージ向上などに貢献した優れた業績を毎年度表彰しております。表彰候補の公募を行い,地盤工学フォーラムでの発表と応募書類に基づき表彰委員会において審査を行い,受賞者を決定します。例年4月頃に開催される東北支部総会で表彰式が行われ,受賞者には表彰状と記念品が贈呈されます。 平成27年度は,以下の通り授賞を行いました。その業績をここに紹介します。 平成27年度 地盤工学会東北支部表彰(技術的業績部門) |
(参考) 歴代受賞業績紹介 / 募集要項,表彰規定等 |
| 受賞者: | 大泉 隆是 | (国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所) |
|---|---|---|
| 須藤 隆之 | (国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所) | |
| 高坂 敏明 | (株式会社ダイヤコンサルタント 東北支社) | |
| 佐藤 春夫 | (株式会社ダイヤコンサルタント 東北支社) | |
| 竹屋 直和 | (渋谷建設株式会社) |
|
東北中央自動車道 東根〜尾花沢間のうち,(仮称)村山IC周辺は,沈降盆地という特殊な堆積環境の中で形成された泥炭性の軟弱地盤であり,長期的に継続する沈下が問題であった。これを抑制するため,地盤内に減圧を作用させることにより,全応力を変化させず,有効応力を増加することが可能な真空圧密工法を採用した。なお,真空圧密工法は,従来問題となっていた沈下の進行に伴う減圧の低下がなく,高い減圧を安定して継続的に作用させることが可能な気水分離方式を採用し,試験施工による検証を行った。 その結果,中間砂層ならびに改良深度による減圧のロスは小さく,改良深度すべてにおいて70kPaの減圧で設計,施工が可能であることが確認された。また,過圧密比の増加により,長期沈下の軽減が可能であることが検証された。通常,サーチャージ盛土の併用は安定の問題が大きいが,真空圧密工法は安定対策効果も高いため,容易にサーチャージ盛土を併用することが可能であり,今後も有効な工法として活用されるものと考えている。 |
|
| 受賞者: | 藤原 聖一 | (奥山ボーリング株式会社) |
|---|---|---|
| 水嶋 清光 | (株式会社ネクスコ・メンテナンス東北) | |
| 太田 徹 | (東日本高速道路株式会社 東北支社 秋田管理事務所) | |
| 澤野 幸輝 | (株式会社ネクスコ・エンジニアリング東北) | |
| 藤原 直哉 | (奥山ボーリング株式会社) | |
| 小松 順一 | (奥山ボーリング株式会社) |
|
開発した削孔システムの最大の特徴は小型・軽量であることである。削孔に用いる資機材の最大寸法は,レールで0.5m×1.5m,最大質量は削孔機の25kgであり,運搬・仮設はすべて,人力による作業を可能とした。この結果,高速道路盛土の施工では資機材の運搬〜仮設までに要する時間は概ね1時間以内であり,緊急性を要する現場における優位性は極めて高い。 これまでの試験施工を含む実績から,崩壊性の地層,硬質な大径礫が混在する地層,硬岩等には適用できないが,それ以外の地層においては施工性,経済性および施工期間において,既存工法と比較して大きな優位性を有していることが明らかになった。施工期間,施工経費は既存工法と比較して,概ね50%程度の短縮,削減が可能で,今後,大きく貢献できる工法である。なお,これまでの削孔長の最長は45mである。 本システムによる集水ボーリング工の計画においては,孔壁の自立性,礫層の場合は礫の硬軟・礫径・礫量,岩盤の場合は固結度等の事前把握が重要で,不可欠であることを付記しておく。 |
|
| 受賞者: | 渡辺 東 | (東日本高速道路株式会社) |
|---|---|---|
| 畠山 剛一 | (東日本高速道路株式会社) | |
| 安田 賢哉 | (株式会社ネクスコ・エンジニアリング東北) | |
| 須山 恭三 | (株式会社大林組 東北支店) | |
| 佐藤 直輝 | (東日本高速道路株式会社) |
|
鳥屋山トンネル (2,600m) は,供用開始の一年半後から路面隆起が確認され,平成26年6月在までに累積で最大187mmの隆起が生じていたため,今回路面隆起が大きい区間を昼夜連続通行止めにより恒久対策(インバート補強工)を行った。 トンネルの地質は,緑色凝灰岩,凝灰質砂岩,泥岩等が分布し,路面隆起箇所の膨張性の調査・試験結果は,凝灰質砂岩で深度約2mでは膨張性粘土鉱物であるスメクタイトを中量含み,その他の試験においても,強い膨張性を示す岩石であることが判明した。 対策工のインバートに使用したコンクリートは,打設後の早期強度発現及び曲げ靭性等を考慮し,繊維入りの高強度の早強コンクリートとした。 インバート施工時の既設覆工コンクリートへの影響解析を,(1) 施工時の再現解析(2次元有限要素法),(2) 変状再現解析(3次元FEM粘弾塑性モデル),(3) 対策工の影響評価(3次元FEM粘弾塑性解析)の結果を踏まえ,平成27年の春季・秋季各20日間の昼夜連続通行止めを行い,施工スパン約5mの連続片押しによるインバート補強工 (126m) を実施した。 |
|
| 受賞者: | 木下 良介 | (東日本旅客鉄道株式会社 東北工事事務所) |
|---|---|---|
| 伊藤 雄太 | (東日本旅客鉄道株式会社 東北工事事務所) | |
| 鈴木 隆裕 | (東日本旅客鉄道株式会社 東北工事事務所) |
|
東北地方太平洋沖地震に伴う津波により甚大な被害を受けた常磐線駒ヶ嶺〜浜吉田間は,内陸側へルートを移設し,新坂元駅〜新山下駅間にある戸花山に戸花山第1トンネル (177m),戸花山第2トンネル (427m) の総延長604mの2本のトンネルを構築した。 当該トンネルの特徴は以下の3つである。
切羽の早期閉合のため上下半交互併進機械掘削を採用するとともに,全線に渡って長尺鋼管先受け工等の補助工法を実施し,2015年9月10日に本体構造物の構築を終えた。 |
|
|
|
|
| 受賞者: | 仙石 昭栄 | (応用地質株式会社 東北支社) |
|---|---|---|
| 境 正樹 | (応用地質株式会社 盛岡支店) | |
| 久木原 峯隆 | (応用地質株式会社 新潟支店) |
|
胆沢ダムは北上川水系胆沢川の上流域に位置し,我が国最大規模の中央コア型ロックフィルダムである。貯水池斜面では,数多くの地すべりブロックが分布することから,湛水時の斜面安定性を確保することが重要な課題となった。 試験湛水時には計12地区67箇所の地すべりブロックを対象に,自動計器による動態観測と巡視を中心とした地すべり監視を行うこととし,「ブロック末端部の重点監視」,「定量的評価可能な点検箇所の設定」,「湖岸斜面の変化を見逃さないこと」を着目点とした監視計画を立案した。 本業務では,点検カルテの作成・使用による地すべり巡視,貯水池斜面の連続空中画像の取得とこれを使用した船上巡視,既存調査資料のGIS化によるデータベース化,速達性のある情報共有などを行った。これらを重層的に運用することにより,貯水池斜面の総合的なマネジメントを行った。 試験湛水時には,対策工未実施箇所も含め貯水池管理上,支障となるような地すべり挙動は認められなかった。 |
|
|
|
|