

|
アクセスカウンタ (since 2000/09/10) |
 トップページ
トップページ
 行事・活動紹介
行事・活動紹介
 行事日程
行事日程
 行事・活動
行事・活動
 地盤工学フォーラム
地盤工学フォーラム
 地盤工学講座
地盤工学講座
 地盤工学セミナー
地盤工学セミナー
 講習会・講演会・見学会
講習会・講演会・見学会
 学術活動
学術活動
 委員会活動
委員会活動
 調査・研究・出版物
調査・研究・出版物
 支部表彰
支部表彰
 受賞業績紹介
受賞業績紹介
 募集要項
募集要項
 社会貢献
社会貢献
 技術協力・連携
技術協力・連携
 出張講義のご案内
出張講義のご案内
 組織
組織
 沿革・規程等
沿革・規程等
 組織・役員・委員
組織・役員・委員
 東北支部 賛助団体 芳名録
東北支部 賛助団体 芳名録
 地盤工学会 特別会員(東北支部分)
地盤工学会 特別会員(東北支部分)
 地盤工学会 本部・各支部へのリンク
地盤工学会 本部・各支部へのリンク
 入会のご案内
入会のご案内
 入会案内はこちら
入会案内はこちら
 東北支部 賛助団体のご案内
東北支部 賛助団体のご案内
 バナー
バナー
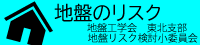


Copyright © 2006-2020 公益社団法人地盤工学会東北支部/Tohoku Branch of the Japanese Geotechnical Society. All Rights Reserved.
掲載日:2009年3月26日(木)
最終更新日:2009年4月20日(火)
| 地盤工学会東北支部では,地盤工学に関する身近で地域に密着した事業・研究等を通じ,
会員の専門技術力の向上,調査・設計・施工等の効率化・レベルの向上,
地盤工学のPR・イメージ向上などに貢献した優れた業績を毎年度表彰しております. 表彰候補の公募を行い,地盤工学フォーラムでの発表と 応募書類に基づき表彰委員会において審査を行い,授賞者を決定します. 例年4月頃に開催される東北支部総会で表彰式が行われ, 授賞者には表彰状と記念品が贈呈されます. 平成20年度は,以下の通り授賞を行いました.その業績をここに紹介します(順不同). 平成20年度 地盤工学会東北支部表彰(技術的業績部門)
|
(参考)歴代の授賞業績・表彰規定等
| 受賞者: | 高田悦久 | (鹿島建設株式会社 東北支店) |
|---|---|---|
| 品川 敬 | (鹿島建設株式会社 東北支店) | |
| 菅原俊幸 | (鹿島建設株式会社 東北支店) | |
| 岡山 誠 | (鹿島建設株式会社 東北支店) | |
| 小林弘明 | (鹿島建設株式会社 東北支店) | |
| 推薦者: | 佐々木隆 | (国土交通省 東北地方整備局 胆沢ダム工事事務所長) |
|
国内最大級の中央コア型ロックフィルダムである胆沢ダム(堤高132m,堤頂長723m,盛立量1,350万m3)は,
冬期の気象条件が厳しいことから年間の施工日数に制限が,コア,フィルタで90日,ロックで173日と制限される. そのため,大型重機を使用した大規模土工の効率化が要求され, 従来の施工管理・品質管理の合理化を重要課題としてITの最新技術の活用を試みている. ブルドーザ,油圧ショベル,振動ローラの施工機械にGPSを搭載し,3D-CADと組み合わせた土工管理システムを採用しており, 必要な情報をオペレータに提供しながら,迅速に大量施工を行っている. これらの導入により,盛立材料の撒出し厚さおよび転圧回数をリアルタイムに重機オペレータが把握することができ, 所定の転圧仕様を確実に満足する結果が得られている.転圧結果は記録に残すことができる. また,IT施工の結果,人と重機の近接作業が激減し,現場内の安全レベルの向上に繋がっている. 胆沢ダムでは,ITの活用による確実な工法規定の遵守により, 盛立材料の採取,仮置き時点での材料選定を重視した管理を行うことで, 盛立面での試験頻度を低減できるロックフィルダムの合理的な品質管理手法を提言している. |
 写真1:3D-MCブルドーザ  写真2:GPS振動ローラ  写真3:盛立状況 |
| 受賞者: | 戸嶋久夫 | (東日本高速道路株式会社 東北支社 鶴岡工事事務所) |
|---|---|---|
| 三浦秀雄 | (東日本高速道路株式会社 東北支社 鶴岡工事事務所) | |
| 太田和伸 | (株式会社ネクスコ・メンテナンス東北 鶴岡事業所) | |
| 永井 宏 | (株式会社ネクスコ・エンジニアリング東北 土木部) | |
| 推薦者: | 鹿島幹男 | (東日本高速道路株式会社 東北支社長) |
|
平成20年8月14日から15日にかけて庄内地方を襲った局所豪雨の影響により,
山形自動車道 酒田地区で供用路線を巻き込んだ約4,000m3に及ぶ大規模な切土法面崩壊が発生した. この地区は庄内砂丘東部を高さ約20mの切土で通過しているが,当時は日本海にあった前線がその南の熱帯低気圧に刺激され, 近傍にあるNEXCOの気象観測所でも時間雨量58mm/h,累計降雨量213mmを記録し,平成9年10月30日開通以来最大の猛烈な大雨であった. 本報文は,砂丘砂での法面崩壊の原因とネクスコグループ会社との協働体制により,本復旧対策を行った結果について述べたものである. |
 写真1:切土法面崩壊の全景写真  写真2:本復旧状況写真 |
| 受賞者: | 草階 勲 | (東北電力株式会社 仙台火力発電所建設所) |
|---|---|---|
| 小野雅毅 | (東北電力株式会社 仙台火力発電所建設所) | |
| 大村英昭 | (東北電力株式会社 仙台火力発電所建設所) | |
| 推薦者: | 田中雅順 | (東北電力株式会社 土木建築部長) |
| 受賞者: | 佐々木順一 | (株式会社 間組 東北支店 土木部) |
|---|---|---|
| 佐久間誠也 | (株式会社 間組 本店 事業本部) | |
| 前田博司 | (株式会社 間組 本店 事業本部) | |
| 澤村祐介 | (佐清工業株式会社) | |
| 推薦者: | 金澤真一 | (株式会社 間組 東北支店長) |
|
仙台市は,薄壁化・本体利用可能なソイルセメント鋼製地中連続壁を日本で初めて採用し,当企業体が施工実績を修めた.
本工事はソイルセメント鋼製地中連続壁工法により自立式の道路擁壁(延長約135m,最大高さ約9m)を構築する工事である.
TRD工法によりソイルセメント壁を原位置にて混合撹拌して造成し,鋼製地中連続壁用鋼材 (NS-BOX) を建込み土留め壁を施工後,
前面を掘削し擁壁(本体利用)とする道路改良工事である. 掘削・芯材建込み精度を1/250で施工し,完成後の変位量は最大で15mm(設計変位量29mm)であった. 岩盤等の硬質な地盤が存在する地域において自立式の擁壁は有効であるが,狭い施工ヤードで, 薄壁・高剛性の壁を構築できる本工法は特に有効であることが施工面からも実証された. 従来のコンクリート充填型の鋼製連壁工法と同様,今後地下道路の壁本体利用の構造物に採用されることで,さらに利用価値を高めることが期待できる. |
 写真1:沿道家屋近接施工状況  写真2:自立式擁壁完成状況 |
| 受賞者: | 瀧田洋一 | (青森県 下北地域県民局 地域整備部) |
|---|---|---|
| 鳥羽瀬孝臣 | (電源開発株式会社 技術開発センター) | |
| 能見忠歳 | (応用地質株式会社 青森支店) | |
| 佐藤 史 | (応用地質株式会社 青森支店) | |
| 三嶋昭二 | (応用地質株式会社 東北支社) | |
| 推薦者: | 曽根好徳 | (応用地質株式会社 東北支社長) |
| 受賞者: | 小泉一人 | (JR東日本 東北工事事務所) |
|---|---|---|
| 瀧内義男 | (JR東日本 東北工事事務所) | |
| 鎌田卓朗 | (JR東日本 東北工事事務所) | |
| 日下郁夫 | (JR東日本 東北工事事務所) | |
| 松尾伸之 | (JR東日本 東北工事事務所) | |
| 推薦者: | 藤森伸一 | (JR東日本 東北工事事務所) |
|
天間川橋りょうは,JR東北本線上北町・乙供間に位置し,一級河川七戸川を跨ぐ鉄道橋である.
今回,河川改修事業に伴い,旧橋上流側に橋長180mの3径間連続PCアーチ橋を建設したものである.
また,前後のアプローチ高架橋,盛土,切取部分も併せて施工しており,全延長約1,200mの工事である. 当該箇所は軟弱地盤箇所であり,川を挟んで極端に支持層の深さも異なるため, 橋梁の構造形式やアプローチ部基礎土構造物についても条件に適合するものを選定している. 主な工事の特徴を以下に示す.
|
 写真1:橋りょう部の全景  写真2:高架橋部の施工状況  写真3:盛土・切取部の施工状況 |
| 受賞者: | 若公崇敏 | (国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所) |
|---|---|---|
| 三浦高史 | (国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所) | |
| 金子和亮 | (日本工営株式会社 仙台支店) | |
| 三浦正徳 | (日本工営株式会社 仙台支店) | |
| 小川 洋 | (日本工営株式会社 仙台支店) | |
| 推薦者: | 山本 聡 | (国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所長) |
|
平成20年6月14日午前8時43分に発生した岩手・宮城内陸地震により,
岩手県一関市厳美町市野々原の磐井川で大規模な河道閉塞が発生した. この河道閉塞は,深さ25〜30mの磐井川を延長約400mに亘って完全に埋没させ, 上流側には貯水容量約180万m3の天然ダムを形成した. また,天然ダムの水位が徐々に上昇していたため, ダム決壊による下流域への土砂災害発生の危険性が非常に高くなっており, 一刻も早い緊急対策工の施工が要求された. 天然ダムの水位監視から,越流までに残された時間は3.5日しかないことが明かとなったため, 緊急対策として,排水ポンプの敷設および仮排水路の掘削工事を同時並行で施工することとした. 計6台の排水ポンプにより天然ダムの水位上昇を約半分程度に抑え, かつ仮排水路の早期通水を目指して24時間施工による掘削作業を進めた結果, 予想より岩盤が硬質であったものの, 6月21日の正午には越流危険水位から2m低いEL258mを敷高とした1次仮排水路(通水能力48m3/s)を完成させ, 無事通水を開始することができた. この1次仮排水路の完成により,河道閉塞の越流・決壊という最悪の事態は阻止できたものの, 梅雨の出水期に向けて,継続して2次断面(通水能力160m3/s)の掘削を行った. この結果,現在では累積100mmを超える降雨時にも安定した通水を確保することができた. |
 写真1:市野々原河道閉塞全景(H20.6.14)  写真2:緊急仮排水路掘削状況(H20.6.20)  写真3:1次仮排水路通水状況 |